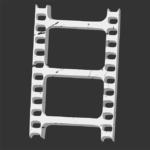映画『イエスタデイ』日本での公開を前に「もしもビートルズがいなかったら」をテーマに放送されたJ-WAVEの「J-WAVE SELECTION THE WORLD WITHOUT THE BEATLES」。NONA REEVES・西寺郷太がビートルズが音楽やライブをやめレコーディングに専念した理由と、その後の世界に与えた影響について解説した。
ビートルズがライブ活動をやめてレコーディングに集中したことの革新性
【サッシャ】それをキャリアの序盤から根本的に塗り替えてしまったということで、じゃあその上で亀田誠治さんに2つ目のコメントを頂いているので行きましょう。
| 【亀田誠治】2つ目です。ビートルズはですね66年のツアーをもってライブ活動を一切やめます。ライブをやめて作品作りに集中する。 こっからです、これまでの作品から大きな違い、それまではやっぱりバンドサウンド、4人で奏でるサウンドというものが、基本にあったのがライブ活動をやめることによって色々なミュージシャンと交わり、色々なオーケストラの楽器を使ったりという、そういう作品作りに集中していくことになります。 要するにアイディアがいっぱい生まれて、そのアイディアをトライ・アンド・エラーして楽曲を作っていくんですね。本当にね今の時代のアーティスト「これがなかなかできてないんじゃないかな」と僕は心配になるんですね。 ライブやフェスで自分たちの音楽を表現して収入を得ていくみたいな、そういうビジネスモデルに今は変わってきちゃったんですけども、肝心の作品を作るということに、今のアーティストは集中できているんだろうか、トライ・アンド・エラーして音源を製作しているんだろうかということが、逆に心配になったりします。 |
【サッシャ】さっきの話と繋がるんですけど、そもそも昔はレコーディング技術があまり発達していないからライブを演ったものをなんとか収めてレコードにしていたからライブがメインだったわけですよね。
それがレコーディングが発達したことによって、ビートルズはライブをやめてしまった。
【西寺郷太】そのライブで作ったものが再現できないというのもあるでしょうし、ライブを演ったとしてビートルズほどの人気があったときに「スタジアムでやります」とか日本でも武道館で演りましたけど、前例がないんですよね。
だから、そこで4人だけで演奏しているものを聴くという習慣がそもそもなかったから、どんなに当時あった大きいアンプを置いたところで、「ギャー」って人が叫んで女の子たちがキャーキャー言っているところで、超うるさいワケですよ。
ビートルズは機材革命でヘヴィな音楽にも影響を与えた
【サッシャ】シェアスタジアムとかみんな聴こえなかったっ話ですもんね。
【西寺郷太】そうなんですよ、そうだろうと、いわゆるモニターシステムなんかも無いんで、ビートルズがやったことで機材も「これじゃ困るよね」ってことで、デカくしたりすることによって、例えばその後のレッド・ツェッペリンとかディープ・パープルとかデカいアンプとかで鳴らして当たり前って音楽が発達していったと僕は思うんですよ。でっかいアンプがあったからヘヴィな音楽が流行りはじめたというところがあると思いますね。
【サッシャ】あと視点を変えてライブをやめた、そうするとライブで再現することから開放された音作りをしはじめたわけですよね。これについてはビートルズはどうですか?
【西寺郷太】それも、それまでいなかったかもしれないですね、逆に。レコーディングで人を驚かせるという、そういうような発想がそれまでのアーティストには、無かったんじゃないかなと思いますね。
ビートルズの『リボルバー』『サージェント』がアルバムで音楽を聴く文化を作った
やっぱり特に1966年の『リボルバー』から67年の『サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブバンド』というアルバムで、「アルバムで音楽を聴く」ということが普通になって、はじめて歌詞カードも付いて、「えっロックの歌詞って、そんな大事なの」みたいな。
【サッシャ】ということは、もしビートルズがいなかったら、今ライブはどうなっていたんでしょうね。
【西寺郷太】どうなっていたんでしょうね。もちろん僕はビートルズ以外も好きですから、さっき言ったようなある種の若者たちが曲を書いて、ユーモア精神で色々なことを無茶ぶりしていったというのは、随分遅れただろうなとは思いますね。
たぶん、その後の黒人音楽とかにも、逆輸入的にかなり影響を与えていると思うので。ビートルズはモータウンに憧れ、モータウンのアーティストもビートルズに憧れて、なんていうのか、お母さんとお父さんから子供が生まれるみたいな。なんか凄く不思議な関係だと思います。だからファクター、ともかく色々な意味でも衝撃的ですよね。
【サッシャ】これから「Tomorrow Never Knows」を聴いてもらおうと思いますけど、これは何が凄いと思いますか?
【西寺郷太】ビートルズにとってインド音楽、一番影響を受けたのはジョージ・ハリスンだと言われていますけど、まあ90年代のサンプリングのヒップホップのようなドラムのループサウンドを繰り返して、リズムが繰り返されるなかにインド的な音階のメロディーが入ったり、世界中の色々な音楽の要素を混ぜながらめちゃくちゃポップ、あと普通にカッコいいという。
それはビートルズがやった一つの冒険のなかで、今新たに僕の子供のような世代が聴いても「なんだこれは」と思えるサウンドになっているかなと思いますね。(つづく)